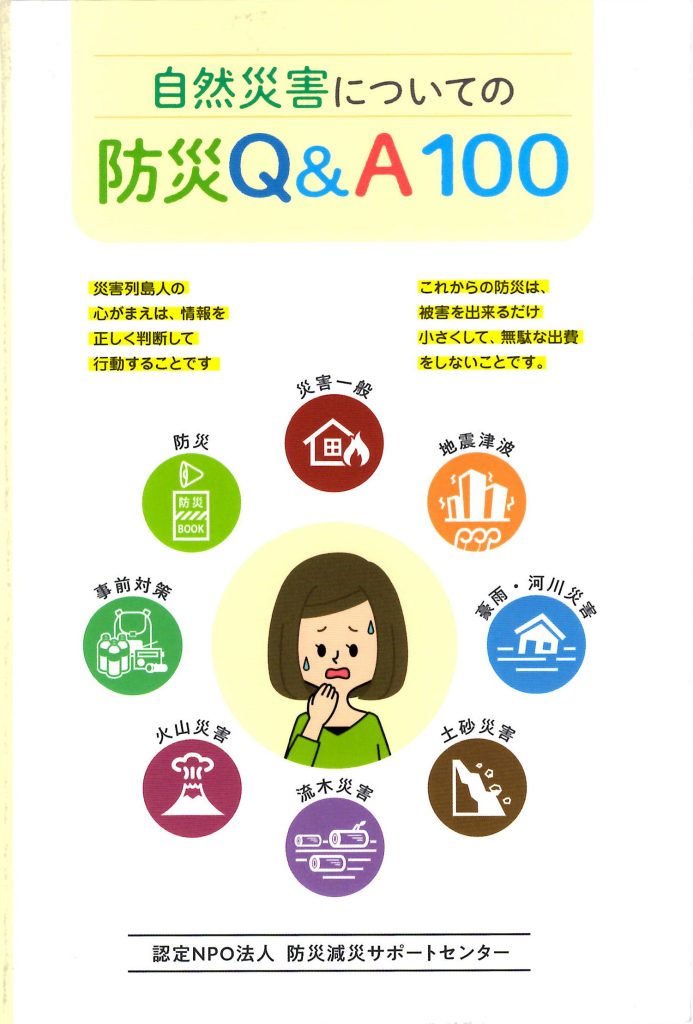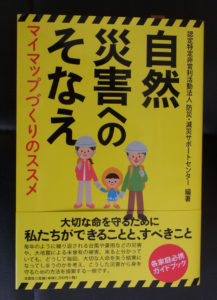ようこそ 防災・減災サポートセンターへ 防災・減災サポートセンターは、地域を自然災害から守りたいの一心で活動する認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)です。町内会や自主防災組織の方を対象にマイマップ(地域の防災マップ)の作成を支援しております。お申し込みは「お問合せ」からお願いします。
2025年12月までの活動報告は、まとめて「2025年の活動」に移動しました。
2026/2/22 New! 東北地地方の太平洋側は最近雨が少なくカラカラに乾燥しています。野外での日の取り扱いに注意が必要です。本日は地質技術者が伝えたいことの10回目「4.防災へのかかわり (3)投資効果」を掲載いたしました。これまでの災害対策と今後の災害対策について、自然環境や社会環境の変化に対応した自然災害対策になっているかを考えていくという主張です。東北大学災害科学国際研究所、北海道大学、海洋研究開発機構の共同研究によると千島海溝付近南西部(北海道太平洋沖)では約400年に一度巨大地震が発生し、最近の観測結果で、M8後半~9クラスの超巨大地震とこれにともなう津波の再来の可能性が示唆されると言う事です。(https://www.tohoku.ac.jp/japanese/2026/02/press20260218-01-seafloor.html)備えを再点検しましょう。
2026/2/15 New! 本日は、地質技術者が伝えたいことの9回目「4.防災へのかかわり (2)ハード対策とソフト対策」を掲載いたしました。砂防ダムや堤防などの構造物による自然災害対策は住民にとって安心をもたらすものではありますが、その対策だけで未来永劫安全を保証するものではありません。既往最大の被害を想定していますので、これを超える災害には効果を発揮できません。そこで、ソフト対策で避難についての基礎的な知識を学び、それによって安全な避難ができるように備えること、ハード対策はそれまでの時間稼ぎととらえてはどうかという提案です。すべてはそこに住んでいる人、訪問している人の地域情報への関心・意識にかかっているようです。ぜひご一読ください。
2026/2/8 New! 本日は地質技術者が伝えたいことの8回目「4.防災へのかかわり (1)なぜ、自然災害が発生するのか」を掲載いたしました。地質技術者は多くの分野にかかわりますが、防災は特にかかわる領域が広く、複雑です。自然災害は人間社会と密接な関係があります。どのように対応していけばよいのか、悩ましいことについて述べています。来月半ばの3月14日(土)には、仙台市が主催する仙台防災未来フォーラム2026が仙台国際センターを会場にして開催されます。当NPOもブースで活動紹介を予定しています。興味、関心のある方はぜひ足をお運びください。
2026/2/1 New! 昨日1月31日(土)午後、仙台市青葉区作並の岩谷堂西地区で11月の現地踏査の結果の報告会を兼ねた防災・減災の講習会を開催いたしました。参加者7名、NPOメンバー7名で講習会を行いました。土石流の警戒区域(イエローゾーン)に地域の一部が指定されているところで、最近の気象変化、ハザードマップについて、踏査結果の概要、この地区の豪雨時の留意点などについて説明し、意見交換を行いました。初対面にも関わらず、和気あいあいとした中で、参加者、講師のみんなが楽しく、充実したひと時を過ごしました。当日は、たいへんおいしい昼食をご馳走になり、NPOメンバー皆感謝いたしました。今後、雪解けを待って豪雨時に土砂災害のリスクのありそうな箇所を一緒に観察する予定で、さらに現地で雨量などの観測も行う計画があるので、災害のリスクをうまく避けることができるよう検討を重ねて行きたいと思います。本日は地質技術者が伝えたいことの7回目「3.地質技術者について」を掲載いたしました。防災・減災に取り組む地質技術者の特徴とモノを見る独自の観点について解説しています。
2026/1/25 New! 本日は地質技術者が伝えたいことの6回目「2.防災と地質学」を掲載いたしました。このNPOは地質技術者が中心となって運営しております。その思いがシリーズで紹介されています。今回は身近にある地形・地質を知ることで、自然災害に強くなれることをご紹介しています。ぜひ身近な地形・地質情報をインターネットで探してみてください。今週末の31日(土)は仙台市青葉区作並岩谷堂西地区で11月に行った踏査の報告会があります。踏査の結果を中心に地域の防災・減災を住民の皆さんと一緒に考えたいと思います。よろしくお願いいたします。
2026/1/18 New! 本日は地質技術者が伝えたいことの5回目「自然現象と災害と暮らし」を掲載いたしました。複雑化してきた現代社会の日本列島に住んでいる私たちは、自然災害のリスクをハザードマップから読み取る必要があり、備えることが大事だといわれていますが、十分にハザードマップを活用するには一定の学習が必要であり、豊富な内容を理解する上では自然科学的な視点が必要なことが強調されています。特に住む土地の情報は重要で、住んでいる場所の旧地形に関心を持つと様々なリスクを小さくできるのではないかと述べています。ぜひご一読ください。
2026/1/11 New! 今回からコラムは再度「地質技術者が伝えたいこと」を掲載いたします。今回は「(2)暮らしの変化」を掲載いたしました。歴史的な観点から最近の気候変動に伴う被害の拡大について述べています。近年の情報化・金融化時代の変化と災害の対象の変化に関連しているのではないかと言う事です。気候変動に関連して、最近米国が世界的な枠組みからの脱退を表明したことが気がかりです。最大の温室効果ガスの排出国であり、その責任は重いと思います。国際法を無視する「心」に頼るしかないのでしょうか。
2026/1/5 New! 新年おめでとうございます。2026年もよろしくお願いいたします。コラム「避難」の2回目です。「あらためて、避難についておもう(2)」を掲載いたしました。「避難学」のご紹介で、これまでの避難に関する書籍と一味違うことをご紹介しています。ご参考になれば幸いです。今月はニューズレターの発行月(原則年4回)です。12月8日に発生した青森県東方沖地震で「北海道・三陸沖後発地震注意情報が発表され1週間継続しました。改めて地震の怖さを思い出しました。ガザでは人道支援の国際NGOの登録でイスラエル政府が厳しい条件を付け、ガザの人道支援が危機状況になっています。また、ウクライナは停戦交渉でトランプ氏とゼレンスキー大統領が協議する予定です。トランプ氏はベネズエラの首都を攻撃し、大統領夫妻を米国に連行しました。戦争が大国の恣意で起こされることに強い憤りを感じます。