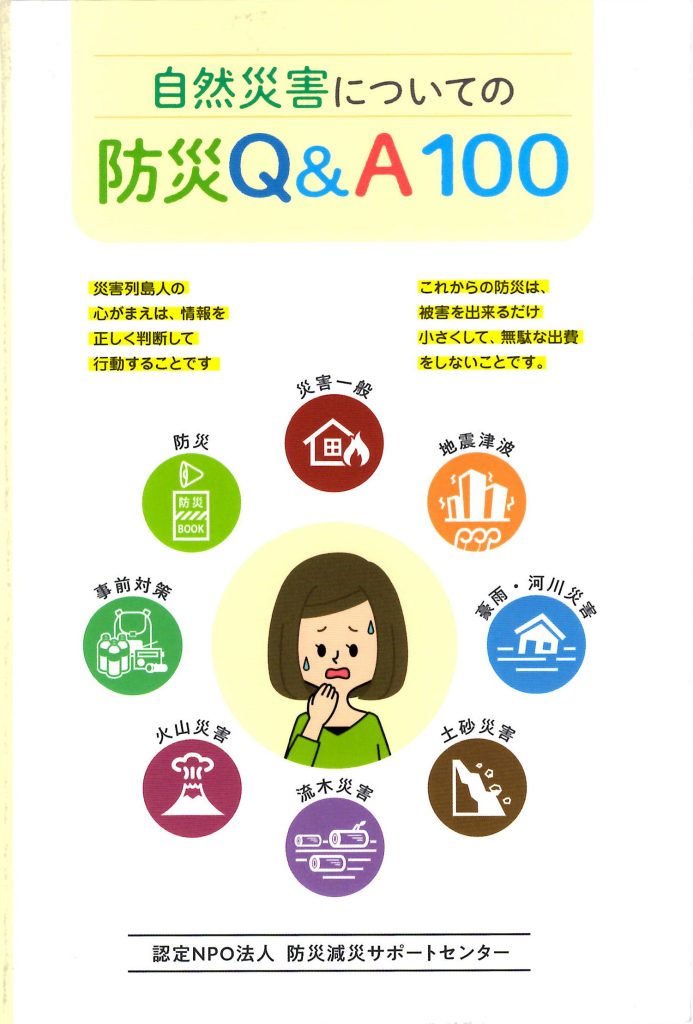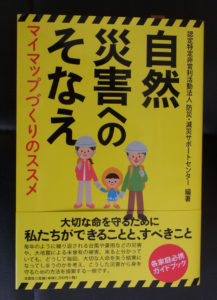2022年1月~12月分をまとめました。
2022/12/26 New! 本日はコラム9シリーズの20回目「国土強靭化とは」を掲載いたしました。自然現象、自然災害と私たちの暮らしから、この意味をもう一度考え直す論考です。「思いつきの防災いろは3」は「な~う」を掲載いたしました。「な;軟弱地盤は何に弱いのか」「ら;落石による被害を防ぐには」「む;むっくりと起き上がる応力開放にびっくり」「う;疑いたくなる怪しい声が隣から聞こえてくる」の4項目です。ウクライナではクリスマスを祝う避難中の市民へのロシアの攻撃が容赦なく続けられています。戦争が早く終わることを祈ります。2023年もよろしくお願いいたします。
2022/12/18 New! 本日はコラム9シリーズの19回目「ハザードマップを死蔵させないために」を掲載いたしました。地域のリスクを知るためのハザードマップは防災・減災には必要不可欠ですが、このハザードマップを上手に使うための方策を考察しています。「思いつきの防災いろは3」は「れ~ね」を掲載いたしました。「れ;劣化はこの世の万物の必定なり」「そ;そこにある地層はなにをものがたる」「つ;つづく大地の変状や変化、その背景は」「ね;粘土の見えないところでの悪さ」の4項目です。寒さが厳しくなりましたが、ウクライナでは市民への電力供給が厳しいようです。NO WAR UKURAINE!!
2022/12/12 New! 本日はコラム9シリーズの18回目「問われることに対して応えるとき」を掲載いたしました。防災・減災の講座や防災マップづくり等の支援で参加された皆さんのご質問にお答えするときの態度について述べています。「思いつきの防災いろは3」は「わ~た」を掲載いたしました。「わ;別れるのには相当な理由(わけ)あり」「か;日本の川が滝に見える?」「よ;余熱、余震、余効、余韻は残り物か?」「た;他山の石は良し、断章取義はだめ」の4項目です。上のメニューからご覧ください。ウクライナではインフラ施設への攻撃で、150万人に電気が供給できない影響が出ています。厳しい冬に入りますが、なんとか早く戦争が終わることを祈っています。
2022/12/6 New! 本日はコラム9シリーズの17回目「河川管理の課題と問題点」を掲載いたしました。河川管理での市民、行政のあり方について考察しています。特に「産」「官」「学」の役割などについて提案をしています。思いつきのぼうさいいろは3は「り~を」を掲載いたしました。「り;災害対応では臨機応変が求められるのはなぜ?」「ぬ;盗んで活かす、似たものやことを探して防災へ活かす」「る;類は類をよぶ、災害現場は広く見るべし」「を;温泉と地すべり、恐怖と恵みのうらおもて」です。ウクライナに対する戦争は、ロシアでは戦争反対が戦争推進を上回ったようです。徴兵が始まってからこの傾向が出てきたようです。早く戦争が終わりますように!
2022/11/28 本日はコラム9シリーズの16回目「これから気になる河川管理」を掲載いたしました。新聞報道の記事から我が国の河川管理について考察したものです。河川の流域特性や文化に思いをはせ、今後の河川管理の在り方に言及しています。思いつきのぼうさいいろは3は「ほ~ち」を掲載いたしました。「ほ;傍若無人なふるまいに理由あり、事前に知ることで減災につながる」「へ;変化に気づく、敏感になる、地獄耳になって早めの判断」「と;土砂は多種多様、多士済々、どこにあるのかで善し悪し判断」「ち;地生態はさまざまなことを教えてくれる正直者です」。ウクライナはミサイル攻撃でインフラが破壊され、これから寒くなる季節に電気が使えないなど、国民に深刻な影響が及んできます。一刻も早く大義なき戦争が終わりますように!
2022/11/21 本日はコラム9シリーズの15回目「これからの社会環境と防災」を掲載いたしました。自然災害への関心と社会環境を国の内外と比較して考察しています。思いつきの防災いろはは、シリーズの3冊目の表紙と目次、「い~に」を掲載いたしました。シリーズ2はひとつにまとめました。ウクライナ情勢はポーランドへのミサイル落下事件がありました。昨日はザポリージャ原発周辺への砲撃が報道されIAEAがロシア、ウクライナ双方へ声明を発表しています。早く戦争が終わりますように!
2022/11/15 本日は、コラム9シリーズの14回目「安藤忠雄(2022.01.01)談(日本経済新聞元旦号第二部)を読みつつ」を掲載いたしました。人類の歴史に比べ、はるかに長い時間をかけて形成された自然を利活用させてもらう時の心得を述べています。思いつきの防災いろはは準備中です。これまでのシリーズをまとめたものを掲載予定です。ウクライナはへルソン州の一部を奪回し、ゼレンスキー大統領が現地を訪問したようです。ロシアがダムなどを一部壊して撤退したとの報道があり、心配しています。早く戦争状態がわることを願っています。
2022/11/7 本日は、コラム9シリーズの13回目「社会の変化を見据えての次世代の防災は?」を掲載いたしました。気候変動による自然環境の変化と少子高齢化を見据えた自然災害への備えについて述べています。思いつきの防災いろはは「も~京」を掲載いたしました。「も:森が健康だと土砂災害も少なくなる」「せ:扇状地の出自を知っておくと付き合いやすい」「す:水害が多くなってきているのにはわけがある」「京:今日の暮らしを見直す勇気」です。(掲載順をこれまでの逆にして、見やすくしました)ウクライナへのロシアの攻撃は激しさを増しているようです。集中的にインフラを攻撃中とのこと。市民や市民生活が犠牲になっています。早く戦争が終わりますように!
2022/10/31 10/29(土)第6回運営会議を開催いたしました。マイマップ(地域防災マップ)づくりを含めた「自然災害への備え」の方法や活用事例を掲載したパンフレットを作成中です。完成は次回の会議を経て来年早々を目指しております。本日は、コラム9シリーズの12回目「岩盤が破壊される・・・」を掲載いたしました。地震の発生から様々な自然災害の備えについて、述べています。思いつきの防災いろはは「み~ひ」を掲載いたしました。「み:水はどこから来るのでしょう、あの山越えて、野を越えて(内水氾濫)」「し:情報は正しい知識で取捨選択」「ゑ:液状化は起きてびっくり」「ひ:被災した自分を想像すると見えるものは・・・・」です。ロシアは穀物輸出合意を停止したそうです。黒海艦隊への攻撃を口実にしています。穀物を待っている国々への影響が心配です。早く戦争が終わりますように!
2022/10/24 10/8~10/18ベトナムでの草の根防災支援活動に参加しました。前回6月下旬に訪問したベトナム北部のラオカイ省の3村でした。このうちの一つの村での中学校での防災紙芝居の様子を写真にしました。とても熱心に見てくれました。本日は、コラム9シリーズの11回目「知識から行動への壁、行動への動機」を掲載いたしました。避難の時の実際は知識だけでは難しく、日ごろの避難訓練やシミュレーションなどの繰り返しが大切だということについて述べています。思いつきの防災いろはは「さ~め」を掲載いたしました。「さ:災害対応の中身を知っておくと役に立つ」「き:帰宅困難者は他人事でない、いつどうなるかのかわわからない」「ゆ:ゆれる地震には力では勝てない、作戦は?」「め:免じて欲しい面的被害」です。ウクライナでは、電力などの社会インフラへのミサイル攻撃で30%の電源が失われたと報じられています。戦争では弱い立場の人々がいつも犠牲になります。早く戦争が終わることを祈ります。

2022/10/16 本日は、コラム9シリーズの10回目「身近な役に立つ地理学的手法」を掲載いたしました。多岐にわたる自然災害への備えで広い視野を必要とする地理学的手法が参考になることを述べています。思いつきの防災いろはは「こ~あ」を掲載いたしました。「こ:洪水と水害は違います」「え:選ぶ、選ばれるには理由があり、旧家と神社は守られる」「て:”てんでんこ”には助かる、助けるための4つの教えあり」「あ:あなたを守るハザードマップは文殊さま」です。ウクライナ南東部での戦いが早期に終結することを願っています。
2022/10/9 本日は、コラム9シリーズの9回目「来るまでわからない、来てからでは遅い」を掲載いたしました。防災情報の3つの大事な項目(発信、伝達、受信と活用)について説明しています。思いつきの防災いろはは「や~ふ」を掲載いたしました。「や:8 つのチェックで一安心、水害時の避難のための備えと注意」「ま:満砂になると砂防堰堤の役割が終わり?」「け:警報はいい送球としっかりキャッチすることが大事」「ふ:ふたごの兄弟、地震と断層」です。ウクライナ情勢は、4州の奪還にむけてウクライナが動いているようです。早く戦争が終結しますように!
2022/10/1 ぼうさい・げんさいニューズレターNo.2を本日発行しました。メニューからご覧ください。また、 本日は当NPOが支援しているラオカイプロジェクトの対象のベトナム社会主義共和国ラオカイ省の行政職員の視察の新聞記事をご紹介いたします。一行は9/24に来日しました。詳しくは河北新報10/1付朝刊みやぎ版の記事をご覧ください。コラム9シリーズの8回目「地域の災害リスクの再認識」を掲載いたしました。地域の防災・減災に関する情報を避難訓練や講習会を通じて共有して、関心を持ち続けることが大事だと述べています。思いつきの防災いろはは「ゐ~く」を掲載いたしました。「ゐ:防災は一朝一夕にはいかない 日常化、風化防止を」「の:のどもと過ぎるまえに熱さを忘れない?」「大雨の降り方には、一発屋と執念深いのがとがある」「く:暮らしと災害は恋仲でもないのにみちづれに」の4題です。ロシアはウクライナ南東部の4州を併合したと発表しましたが、国際社会では認められないでしょう。部分的動員命令でロシアは混乱しています。戦争が早く終結するように祈りたいです。

2022/9/23 本日は、コラム9シリーズの7回目「ことばで防災への思いを伝えたい」を掲載いたしました。慣用句やことわざに防災・減災の教訓的なものがあります。これを少し集めてみました。思いつきの防災いろはは「な~う」を掲載しました。「な:何のために、何をどうつなぐかが地域防災の基本」「ら:来年のことをいうと鬼が笑う、いつ来るかわからないことをいったら鬼はどうする」「昔の人の防災は観天望気の観察力」「雨水は方円の器に従う、邪魔されず早く海にいきたいのに」の4題です。ウクライナ情勢では、プーチン氏が予備役30万人の招集を決めました。隣国への航空機が満席のようです。早く戦争が終わりますように!
2022/9/15 9月10日(土)に第5回運営会議を開催いたしました。主な議題はマイマップづくりの新パンフレット(第4版)案の検討、ニューズレターNo.2の内容等でした。この後、出版記念の会と中里さんをしのぶ会を開催いたしました。コロナ対策をしつつ9名が参加して、盛況でした。本日は、コラム9シリーズの6回目「災害に備えることは、暮らしを変えること」を掲載いたしました。自然災害は今後も巨大化するのに対応して、我々の対応をどのように変化させることが大事かを述べています。「思いつきの防災いろは」は「れ~ね」を掲載いたしました。ウクライナは、反転攻勢にでて東部地域を奪還しているようです。ザポリージャ原発は電源が確保され、冷温停止に向かっているようです。戦争状態が一刻も早く終結するよう祈っています。
2022/9/5 本日はコラム9シリーズの5回目「経緯から学び、古人の行為を今に生かす」を掲載いたしました。私たちの生活の場である平地での歴史的な情報から地域知が生まれ、これを現代の私たちが上手に生かすことについて述べています。「思いつきの防災いろは」は「わ~た」を追加掲載しました。10日は書籍「自然災害のための防災Q&A100」の出版記念の会と故中里理事のしのぶ会を石巻市の飛翔閣で開催いたします。ウクライナ情勢では、ザポリージャ原発の監視にIAEAが駐在することになったようです。原発への攻撃がされないことを祈ります。
2022/8/28 本日はコラム9シリーズの4回目「災害は、思わぬ弱点を見せてくれる、過去から学ぶことの意味」を掲載いたしました。古文書を含む災害履歴とさらにさかのぼって、地形や地史に刻まれた災害履歴を知り、リスクを知っておくことは重要ですが、必ずしも既往のものが最大の災害ではないことを念頭に災害への方策を考慮する必要性を述べています。思いつきの防災いろはは「り~を」を追加しました。NPT会議で合意文書がロシアの反対で採択されず閉会したことは本当に残念です。ロシアがザポリージャ原発を攻撃していることも許せない行動です。何もできませんが早期の戦争終結を願うばかりです。
2022/8/22 本日はコラム9シリーズの3回目「潜在化したものは顕在化する機会を待っている」を掲載いたしました。見えない自然災害リスクを明らかにして土地のゾーニングによって安全な暮らしを求めることの大切さを述べています。「自然災害についての 防災Q&A100」の出版記念の会を9月10日に石巻で開催する予定です。一緒に活動してきた故中里さんをしのぶ会も併せて開催します。「思いつきの防災いろは」の「ほ~ち」を追加掲載いたしました。
2022/8/12 本日は当NPO法人で出版した「自然災害についての 防災Q&A 100」をご紹介いたします。町内会や市民センターで開催した防災・減災講座のときにいただいた質問にお答えする形で、100問100答の形式で説明しております。自然災害の防災・減災のいろいろな場面でぶつかる疑問・質問がかなり網羅されています。疑問・質問の関心のあるところから、ぜひご一読ください。仙台の金港堂書店で入手できます(1冊1000円+税)。また、本日はコラム9シリーズの2回目「基本形を持つことで応用ができる」を掲載いたしました。地域防災で地域のリスクを知り、地域の人が話し合いながら防災力を高めることを、普段から実践することの重要性を指摘しています。防災いろはの連載を更新しました。8日(月)のマッチング会議では宮城県の北部の小中学校や公民館の担当の方と自然災害の防災・減災の支援について面談いたしました。支援の要請をお待ちしています。ウクライナは南部で反転攻勢と聞きますが、ロシアが原発を標的にするようなことが聞こえてきます。これは絶対あってはならないことです。早く戦争が終結しますように!
2022/8/5 本日はコラム9シリーズの掲載を始めます。「防災いろは」は別コーナーで掲載いたします。コラム9シリーズの第1回目は「同時多発的複合災害がおきることを想定したことがあるか」です。さまざまな自然災害が並列的に起きること、つまり豪雨時に同時に巨大地震が発生するというような場合です。このようなときの対処の仕方について述べています。8/8(月)はみやぎ教育応援団のマッチング会議(宮城県大崎合同庁舎)に参加予定です。防災・減災活動でご協力させていただきます。ウクライナの南部の港から穀物を積んだ貨物船が出港して、エーゲ海まで到達したようです。これからも無事に穀物輸送ができること、戦争が早く終結することを願っています。
2022/7/27 本日は、ニューズレターでご紹介した「防災いろは」のまえがきと目次を掲載いたしました。「おもいつきの防災いろは」は2022年の正月に冊子として刊行しております。詳しくはお問い合わせください。今回の掲載はこの続編というべきもので、今後2項目ずつ掲載を予定しております。ご期待ください。ウクライナでは南部の港湾がまた攻撃を受けたようです。穀物の輸出に関係するので、早期の解決を願っています。
2022/7/19 7/17(日)学都仙台宮城サイエンスデイ2022(第16回)に講座を出展しました。タイトルは「地震を見る、聴く? ~ゆれる波の正体とは~」で地震の発生から地震波の伝わり方、地震によって起きる建物被害(固有周期)、液状化などの現象を解説しながら、簡単な実験装置で再現しました。午前12名、午後12名の参加で楽しく実験ができたと思います。サイエンスデイ全体では4,900名の参加者でした。7/1にニューズレターを発行しました。会員の皆様にはお送りいたしました。今後、活動の広報を兼ねて、年4回程度発行の予定です。よろしくお願いいたします。


2022/7/12 7/5,7/8の2日間にわたって、石巻市立住吉小学校の総合学習の時間で防災学習(マイマップづくり)の支援を行いました。4年生11名の参加で、5日は座学の授業、8日はフィールドワークとまとめでした。皆さん一生懸命に取り組んでもらい、地域の防災・減災に興味を持ってもらえたと思います。本日は、コラム8シリーズの最終回「防災教育のポイント」を掲載しました。防災教育の4つの目標と防災意識を高めるための展開について述べています。マイマップづくりは理想的な防災教育の一つの典型です。皆さんも取り組んでみてはいかがでしょうか?17日(日)はサイエンスデイ2022へ出展します。申込制の講座です。



2022/7/4 6/18~7/2ベトナムでの草の根防災支援活動に参加しました。ベトナム北部のラオカイ省の3村でした。明日7/5は石巻市住吉小学校の防災学習支援(座学)です。地域情報を学びながら、自分と家族の身を守ることを伝えたいと思います。マイマップづくりを中心に8日にはフィールドワークも計画中です。コラム8シリーズは12回目「わが国の自然災害と暮らし」を掲載しました。人の生活と自然災害について、考察しています。ラオカイの高地(標高1000~1500m)の村では地すべりと土石流が主な自然災害ですが、たいていの場合住宅の移転を選択するようです。これも一つの対策です。ウクライナ情勢は東部での攻防が激しくなっていますが、被害は市民が被っています。一刻も早く戦争をやめてほしいです。


2022/6/14 6/11(土)に住吉小学校周辺の防災マップづくりの踏査を実施しました。その後、石巻市かわまち交流センターで第3回運営会議を開きました。今後の活動の内容について検討しました。7/5、7/8に住吉小学校の総合学習の時間で防災マップづくりを支援します。そのあと7/17(日)はサイエンスデイ2022に講座型プログラムで出展し、「地震を見る、聴く?~ゆれる波の正体とは~」というタイトルでお話や実験を計画しています。サイエンスデイ2022のHPから申し込みが必要です。本日はコラム8シリーズの11回目「災害を風化させずに伝えていくために」を掲載いたしました。伝えられた災害の事実を聴き手が自分事として能動的に受け止める大切さを述べています。世界のパン篭のウクライナの小麦などが滞って、値段が高騰しアフリカなどでは飢餓が広がっているようです。一刻も早く戦争が終わることを心から願っています。
2022/6/7 本日はコラム8シリーズの10回目「自然災害による被害の新顔」を掲載しました。社会構造や気象の変化などで、これまでにない新しい自然災害(長周期地震動による高層建物のゆれ、内水氾濫、谷埋め盛り土のすべりなど)の発生と避難時の情報の発信、受け取りの課題について論じています。ウクライナは東部で勢いを盛り返しているようですが、長期になるような気配です。食料やエネルギーに大きな影響があり、いつも困るのは貧困などにあえぐ人々です。一刻も早くこの戦争が終わることを願わずにはいられません。今週11日は石巻市住吉小学校の予備踏査と第3回運営会議が開催されます。
2022/5/30 本日はコラム8シリーズの9回目「経験したことのない大災害に遭遇すると・・・」を掲載しました。長い歴史を経てきた地形は過去の災害の証人で、学ぶべきものは多くあります。しかし、災害は全く同じように発生するわけではないので、事前の準備が大切で、これを応用して対処することが重要であることを論じています。参考にしてください。ウクライナの東部戦線は厳しさを増しています。戦闘が終結することを祈るばかりです。
2022/5/22 本日はコラム8シリーズの8回目「課題解決への過程を楽しむ」を掲載いたしました。様々な組織・団体で防災に取り組んでいる方たちへのメッセージです。いろいろな方と接していく中で課題や問題点が明確になりますが、この際に大事な三つのことを述べています。読んでみてください。ウクライナ東部はロシアが制圧したと聞きますが、ウクライナの人々は徹底抗戦の構えのようです。心からウクライナを支援したいと思います。
2022/5/16 第15回通常総会(2022年度)は5月14日に無事終了いたしました。総会資料はここをご覧ください。なお、当日の参加者は委任状14名を含む正会員19名全員出席でした。ご協力ありがとうございました。総会に先立つ運営会議では、7月上旬に予定されている石巻市住吉小学校の防災学習支援、ニューズレターの作成・配布などが検討され、実施することが決まりました。本日はコラム8シリーズの7回目「役割分担の大切さ」を掲載いたしました。町内会や自主防災組織の活動での役割分担の大切さと、普段の活動が地域の災害復旧や復興でも重要な役割を果たす基になることが述べられています。ウクライナ情勢に関連してと思われますが、フィンランドとスウェーデンがNATOへの加盟を急いでいるようです。緊張がさらに高まるのではと危惧しています。
2022/5/9 今週5月14日(土)は、当法人の第15回通常総会が開催されます。会場は日立システムズホール仙台(仙台市青年文化センター)会議室3で、午前11時開催(受付10時30分~)です。ご出席よろしくお願いいたします。正会員でご欠席の場合は、委任状をお送りください。本日はコラム8シリーズの6回目「人間と森林の関係から見えてくるもの」を掲載しました。地域の主たる環境は森林であり、人間の働きでバランスが崩れると人の生活を脅かすことになると論じています。気候変動とあいまってバランスを崩しそうな森林環境を深く理解した行動が大事です。ウクライナでは学校が爆撃され避難した多数の人が犠牲になりました。国連の事務総長が言ったように、戦争で一番の被害を受けるのは一般市民です。戦争絶対反対!!
2022/5/2 本日はコラム8シリーズの5回目「素因を知れば思いがけないことも想定外にはならない」を掲載いたしました。自分たちの住んでいる地域の災害リスクを知るために、災害の素因(地形や地質などを知っておくと、地震や豪雨などの気象現象に反応して発生する自然災害をあらかじめシミュレーションして備えることができることを述べています。地域の災害履歴と合わせて自然災害に備えましょう。ウクライナ情勢は長引きそうですが5/9がひとつのポイントになるようです。注視したいと思います。
2022/4/24 本日はコラム8シリーズの4回目「コロナ禍を活かした危機管理」を掲載しました。これまでの人類が経験してきた環境変化への対応と、様々な自然災害への対応の類似性について論じています。「共生」がひとつのキーワードになるのではないかと述べています。マリウポリでは徹底抗戦が報られていますが、住民も多数残っているようで気をもんでいます。国連事務総長の訪問の効果が上がることを期待しています。
2022/4/17 本日はコラム8シリーズの3回目「地域のリスクを話し合う」を掲載しました。地域の高齢化と自然災害について、日ごろのお付き合い(地域コミュニティ)の大切さについて述べています。ともすると日常の生活に忙殺されがちな毎日ですが、高齢者も安心して暮らせる地域社会の大切さを考えさせられます。ウクライナ情勢の悲惨さが日常化してきたように思います。この時間にも爆撃や戦闘が行われています。世界を見回すと紛争などで安全・安心な暮らしができていない地域がたくさんあることに気がつきます。平和の尊さを感じるこの頃です。
2022/4/11 本日はコラム8シリーズの2回目「里山を生産林に」を掲載しました。森林環境と里山、自然災害の観点から見てみる必要性を述べています。ロシアのウクライナ侵攻は東部で激しくなっているようです。撤退した後に判明した残虐な行為は史上まれなものです。難民となった方が、日本にも来られたようです。早く戦争が終わることを祈りたいと思います。本日はトップページの右上のカレンダーをやめ、今後の予定を記入することにしました。予定を2~3回、過去のイベントを2回掲載します。今後もよろしくお願いいたします。
2022/4/3 新しい年度が始まりました。異動などもあり、新たな環境で張り切っている方もおられると思います。当法人も5月の総会にむけて準備中です。地震の新たな予測が公表され、津波の高さが従来よりかなり高く想定された地域もあります。気候の変化とともに風水害も激しさを増していますので、もう一度備えを確認していただきたいと思います。ウクライナ侵攻は1か月を過ぎても激化しており停戦の見通しが立たないようです。ロシアでは情報が統制されているようで、正確な情報が国民に伝わっていないようです。とにかく戦争は絶対反対です。本日はコラム8シリーズ「基は元なり~きた道を知り、いく道を見据える~」の第1回目「暮らし方を見直す」を掲載しました。コラム筆者の言葉を引用してコラム8シリーズのテーマを記します。「自然災害に対する備えということからすると、一番に効果的なことは経験を生かすということ、そこから学習することの積み重ねであることを再認識しておく必要があると思います。」
2022/3/23 3/16深夜にM7.3の地震が福島県沖(宮城県境に近い)で発生しました。最大震度は登米市などで6強でした。投稿者の住宅付近でも大きな揺れに見舞われました。書棚が倒れれたり食器棚が倒れることはありませんでしたが、水槽の水があふれ、タンスが5㎝程移動したりしました。配水池の配管が損傷して、断水が約20時間続き、水のありがたさを改めて思い知りました。宮城県はもちろん福島県、岩手県の沿岸にお住いの方々にお見舞い申し上げます。本日はコラム7シリーズの13(最終回)の「改めて防災について」を掲載いたします。自然災害への対策とそのメリットデメリット、限界などとともに、市民科学をとおした一人ひとりの関心の継続の大切さを述べています。次回からコラム8シリーズが始まります。
2022/3/16 ウクライナへのロシアの侵攻が日ごとに激化している様子がニュース報道で流されていますが、信じられないような惨状です。目の前で殴られているのを黙ってみているような気になります。できることは寄附くらいですが、少しでも早く停戦ができることを願っています。本日はコラム7シリーズの12回目「人新世と自然災害」を掲載いたしました。最近の気候変動と地質時代の気候変動を考え、自然現象の激化と自然災害について考え、我々の意識改革について述べています。
2022/3/10 仙台未来防災フォーラムに参加しました。当日はコロナ感染予防の影響で、一部で出展者自身が出展を見合わせていたようです。私たちは学校の防災教育支援の立場から現状の課題を考えてみました。地域と学校の相互の協力が有効な防災教育になるような気がします。地域のキーマンが活躍する場だと思います。本日は、コラム7シリーズの11回目「SDGsの中での防災」を掲載いたしました。防災においてもSDGsの視点が大切なことを論じています。


2022/2/28 本日はコラム7シリーズの10回目「わかっていることにどう対応するのか」を掲載しました。来ることがわかっている自然災害に対して、対応するには何が重要なのかを考えます。今週土曜日(3/5)は仙台未来防災フォーラムが仙台国際センターで開催されます。9時30分~16時30分で、ブース展示に参加します。コロナの感染が心配ですが、十分注意して展示したいと思います。
2022/2/20 3月5日(土)、仙台国際センター展示棟で仙台未来防災フォーラム2022が開催されます。当法人もブース展示で参加します。テーマは「小・中学校の防災授業支援と課題~マイマップづくりと防災実験」です。これまで実践してきた小・中学校の総合的な学習の時間を利用したマイマップづくりや実験をご紹介します。また、地域をキーワードにした座学やフィールドワーク、マイマップづくりで感じた課題と提案も併せてご紹介します。本日はコラム7シリーズの9回目「防災から見ての環境保全構想」を掲載いたします。脱炭素社会を目指すために必要な地域の環境財(人材、組織、もの、情報)の活用について論じています。
2022/2/10 本日はコラム7シリーズの8回目「地方創生と安全環境」を掲載いたしました。コロナ禍でライフスタイルを見直す機運が高まっていますが、「地方創生」と災害リスクについて考察しています。コロナがまだまだ収まりそうにないこの頃ですが、いつか来るコロナ後に備えて様々な準備をしておきましょう。
2022/1/28 1月31日(月)と2月4日(金)に予定されていた仙台市立南光台東小学校6年生対象の理科授業支援(防災・減災関連)は新型コロナの猛威で、仙台市や宮城県での感染者の急増の関係で中止のやむなきに至りました。地震波、液状化、建物の揺れの実験を準備していたので大変残念です。今後、別の機会に支援で活用したいと思います。本日はコラム7シリーズの7回目「自然災害は相手を考えないデストロイヤー」を掲載いたしました。ライフスタイルやコミュニティ、社会全体のありかたが変化していく中で、自然災害への対応を考察しています。
2022/1/19 新型コロナのオミクロン株が猛威を振るっており、油断できない日々が続いています。また、トンガでは火山の噴火が発生し、津波が発生しました。松島湾でも養殖いかだが被害を受けました。本日はコラム7シリーズの6回目「7-6 自然現象は天からの贈り物、賢く生かす」を掲載しました。長い地球の歴史と私たち人類の関係、特に自然災害と私たちのライフスタイルの関係について防災の観点から論じています。
2022/1/10 あけましておめでとうございます。本日はコラム7シリーズの5回目「7-5 「防災」を当たり前にする」を掲載いたしました。防災への対応を、人の健康管理にたとえて、普段から関心を持つことの大切さを述べています。